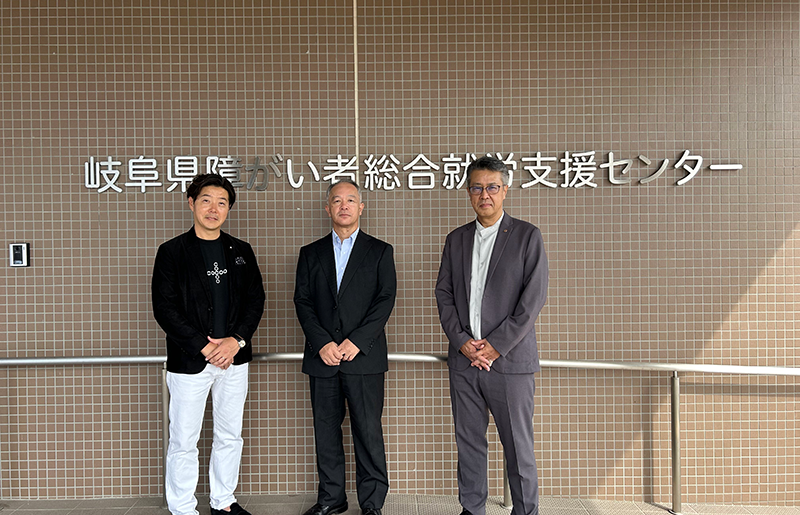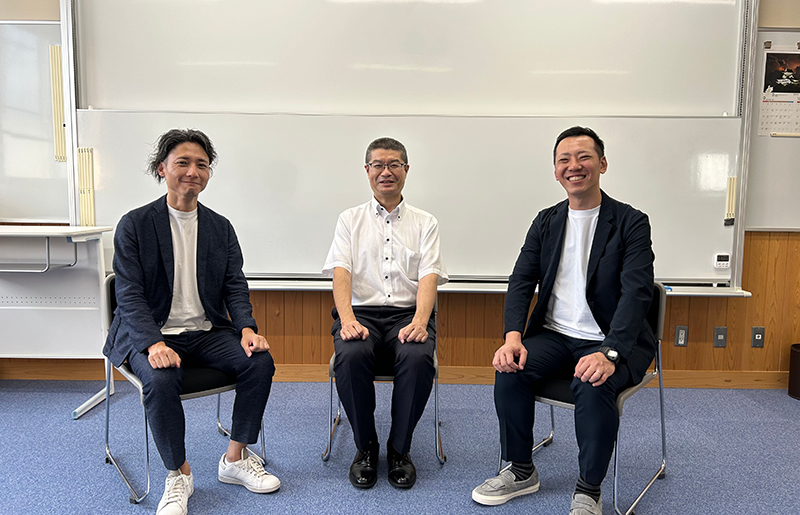この度、コクー社は、岐阜県の「障がい者職業能力開発校」様に、障がい者の方への職業能力開発の支援として、ITリテラシーの習得に関する講座をご提供しました。そこで、今回の講座を企画いただいた「十六電算デジタルサービス株式会社」様にもご参加いただき、岐阜県の障がい者の職業能力開発について対談を行いましたのでご紹介します。
インタビュー
コクー株式会社
代表取締役CEO
入江 雄介
岐阜県障がい者総合就労支援センター 所長
岐阜県立障がい者職業能力開発校 校長
大橋 正敏氏
十六電算デジタルサービス株式会社
代表取締役社長
西部 里美氏
入江: 障がい者職業能力開発校様はどのような役割をもって設立された組織なのでしょうか?
大橋さん:
岐阜県では、障がい者雇用に係る取り組みとして、「就労に向けた相談支援」、「雇用促進に向けた企業支援」、「障がい者の技能習得支援」の3つを主体に支援事業を実施しています。そして、開発校を、障がい者の技能習得支援機関として、障がいのある方々の就労を総合的に支援する岐阜県障がい者総合就労支援センター内に設置しました。
入江:
とても綺麗な施設ですが、何年に設置されたのでしょうか?
大橋さん:
ありがとうございます。令和2年4月に設置しました。

入江: 具体的には、障がい者の方にどのような技能習得支援を行われているのでしょうか?
大橋さん:
一般就労を希望する障がいのある方に対して、個々の障がい特性や能力、適性、目指す就労分野に応じて、就職後の職場定着や社会生活の充実も見据えながら、1年間の職業訓練を実施し、企業等で活躍できる実践的な能力を身につけた職業人を養成しています。
具体的には、「基礎実務科」、「OAビジネス科」、「Webデザイン科」の3つの訓練科を設置しております。「基礎実務科」では、パソコン基礎、簡易事務、介護・清掃、販売などの訓練を、「OAビジネス科」では、パソコン、簿記会計、応接の基本など事務職に必要な知識と技能の訓練を行います。そして、この度、コクー株式会社様に、ITリテラシーの習得に関する講座をご提供いただいた「Webデザイン科」では、Webページの制作、印刷物のデザインの訓練をし、コンピュータを用いた仕事に必要な知識と技能を身に付け、Web制作技術者、デザイン印刷オペレーター、Webページの更新やチラシ制作ができるような事務員を目指しています。
コクー株式会社様には、5回にわたり訓練を実施していただき、仕事で実際に使うコンピュータ関連の知識の習得や、仮想でサーバの構築体験をしたり、ネットワーク設定を行うなど、実践的な訓練をしていただき、訓練生にとって大変、有意義であったと思います。ありがとうございました。
3科とも、全ての障がい者を対象とした少人数制の訓練科となっており、丁寧なアセスメントに基づき、個々の障がい特性に合わせた訓練を実施しております。また、訓練生が希望する職種分野の中から職場見学・体験や職場実習を行って、その企業が求める能力を身につけるための訓練も行っています。また、パソコンなどの技能訓練に加え、社会人として必要なビジネスマナーや職業生活で必要なコミュニケーションスキルやストレス対処スキル等を学ぶ社会適応訓練を行っております。

入江: 障がい者総合就労支援センターさんの中にはハローワークなども設置されているのですね?
大橋さん:
はい。「岐阜県障がい者総合就労支援センター」には、本校の他に、職業紹介を行う県立ハローワーク、障がい者を雇用する企業と企業で働く障がい者を支援する岐阜県障がい者雇用企業支援センター、障がい者の就業と生活を一体的に支援する障害者就業・生活支援センターを設置しております。センター内の支援機関が連携して、本校の訓練生はもちろん、障がいのある方々へ総合的な就労支援をご提供できる体制を整備しています。
また、施設内には、寄宿舎も用意しておりますので、遠方にお住まいの方等で通学が難しい方にも訓練を受けていただける環境を整えております。
入江: 岐阜県の障がい者雇用や職業訓練において、開発校様に期待される役割についてお聞かせいただけますでしょうか?
大橋さん:
皆さまもご存じかと思いますが、日本の障害者の法定雇用率は、令和6年4月から2.5%、令和8年7月から2.7%と段階的に引き上げられることになっています。そのような背景のなかで、量的要素だけではなく、障害者雇用の質を高めることが求められております。
岐阜県では、「岐阜県障がい者雇用企業支援センター」が、障がい者を雇用する企業に対し、雇用に向けた受入体制整備のアドバイスから、障がい者の力を引き出す仕事づくり、職場定着を担う支援機関とのネットワーク構築などを支援し、企業の障がい者雇用の質の向上の支援に取り組んでおります。
本校でも、職場における能力発揮、キャリア形成、職場定着などに寄与できるように、働く時に必要となる知識、技能の習得に係る訓練に加え、職業生活に必要なビジネスマナー、コミュニケーション、自己理解等のスキルを高める社会適応訓練を手厚く行っています。
入江:今回の講座は、十六電算デジタルサービス株式会社(JDDS)様にて企画いただいたものですが、JDDS様はデジタルソリューションを通してDX推進を支援されておられますよね?
西部さん:
はい。JDDSは、岐阜・愛知を地盤とする十六フィナンシャルグループの一員として、地域のデジタル化とDX推進を支援する役割を担っています。当社は2022年3月に、十六フィナンシャルグループと電算システムホールディングスの合弁により新たなスタートを切りました。
地方銀行と上場IT企業の合弁による他業銀行業高度化等会社としては、全国初の試みです。
JDDSのミッションは、デジタル化やDX推進に取り組む事業者や行政を支援し、地域の課題解決に貢献することです。地域に根ざしたIT企業として、お客さまの業務プロセスを可視化し課題を明確にしたうえで最適なソリューションを提供することに重きを置いております。

入江:地域のデジタル化とDX推進を支援されてこられたJDDS様が、今回の講座企画をご提案された背景はどのようなものだったのでしょうか?
西部さん:
JDDSでは、2022年3月のデジタル事業取組み開始以来、地域のIT人材不足を痛感していました。そうしたなか、当社では毎月「世の中問題研究会」という勉強会を開催しているのですが、その勉強会で障がい者の方の就労支援への取組みを取り上げる機会があり、障がい者の方とITとは親和性が高いことを学びました。
このIT人材不足と障がい者の方々の社会参加という二つの課題をうまく組み合わせるとwin-winでの解決が図れるのではないかと考えたのがきっかけです。また、開発校様の前面道路を私が、たまたまジョギングコースにしていたこともきっかけの一つです(笑)。このアイデアをもとに、岐阜県様およびコクーさんにご相談させていただき、今回の講座開講となりました。
入江:
そうなのですね。弊社コクーもIT人材不足という社会課題に貢献したいと考えて、人材育成から企業様の支援までご提供しておりますが、障がい者の方とITとの親和性という観点については、新たな気づきをいただきました。
そして、開発校様とはジョギングコースでのご縁もあったのですね(笑。
入江:JDDS様はどのような期待をもって、開発校様に講座提供を支援されたのでしょうか?
西部さん:
JDDSでは、岐阜市が支援する「テレワークを活用したショートタイムワーク事業」に参画して人材を募集しており、育児や介護などの理由で労働時間に制約のある方やテレワークで働きたい方の社会参加機会を提供させていただきたいと考えておりました。
特にWebデザイン科で学ばれている方々のスキルと実際のビジネスを掛け合わせると、ご活躍いただける場が多いのではと考えております。
JDDSでは、すでにテレワークやフレックスタイム制を導入し、自らのワークライフに合わせて、柔軟な働き方ができる環境を整えてきております。多様な人材が働きがいをもって活躍できる職場づくりをする企業が増えれば、各地方におけるIT人材不足の解決に僅かながら貢献できるのではといった期待を込めています。
入江:開発校様として、今後の展望などをお聞かせいただけますでしょうか?
大橋さん:
人口減少が加速するなか、多くの産業で人手不足が深刻化しています。そのため、障がいのある方もない方も、職に就いて社会で活躍していただくことが期待されています。西部さんのお話のとおり、デジタルの力の活用により、その方々の障がいの状況に合わせて、柔軟な働き方ができる環境が整えられれば、就労が難しいと思われていた障がいがある方にも就労いただくことができます。
Webデザイン科の修了生で、障がいにより、毎日、通勤が難しいため、テレワークでデータ入力業務を行う会社に就職された方がいます。
近年は、職を求める障がい者は年々増加しており、特に精神障がい者の伸びが顕著です。本校においても精神障がい者の方の割合が増えております。精神障がいの方には、対面で人と接することにストレスを感じる方も多くみえますので、そういった方には、テレワークを活用した就労は有効だと考えます。
障がい者を雇用する企業には、障がい者が働きやすい環境の整備を含め雇用の準備を整えていただき、障がいのある方は就労の準備を十分に行ない、量的要素だけではなく、障がい者雇用の質を高めてくことが重要となっています。
先程も申し上げましたが、本校としては、障がいのある方が就職後も安心して長く働き続けることができるような就労準備の支援も含め、個々の障がいの状況に応じたきめ細かな職業訓練を行ってまいります。
入江:JDDS様はいかがでしょうか?今後の展望などあればお聞かせいただけますでしょうか?
西部さん:
人口減少社会問題は、経済的には消費パワー不足問題と担い手不足問題の両面で捉えられます。担い手不足問題への打ち手としては、デジタル化による生産性向上と多様な人材の社会参加を促すことが重要な解決策となります。また、消費パワー不足問題についても、障害のあるなしに関わらず、誰もが消費パワーを持つ側に回ることができれば、一つの解決策となり得ます。
個々の力はさほど大きくなくても、多様な方々がそれぞれのもちまえを発揮し、それを集結させれば、大きな力になります。当社ではこれを漫画「ドラゴンボール」になぞらえて、「元気玉戦略」と呼んでいますが、この実現により、人口減少社会問題解決の糸口にできるのではないかと考えております。
こうした活動を通して、十六フィナンシャルグループが掲げる「お客さま・地域の成長と豊かさの実現」を目指してまいります。
入江:
「元気玉戦略」というネーミング、素晴らしいですね。

西部さん:コクーさんも地方創生への取り組みをされておられますが、岐阜県を含めた地方支援について今後お考えのことなどはありますか?
入江:
ありがとうございます。
弊社は、「VISION 2030」でDX人財輩出企業No.1を目指していて、その重点テーマの一つが「地方創生」です。 2030年までには30拠点を立ち上げるという目標(KPI)を持ち、2024年10月1日に地方創生DX室を立ち上げました。日本のGDPの約7割を地方が担っていることを考えると、地域を元気にすることが日本の元気につながると信じています。私たちはDX人財の”地産地消モデル”で地銀グループ様をはじめ、自治体や地元有力企業様との協業を通じてそれを実現したいと考えています。
また引き続き岐阜県の皆様ともご一緒させていただき、日本を元気にしていきたいですね。
本日は皆様お忙しいところ、ありがとうございました。
※取材日:2024年9月